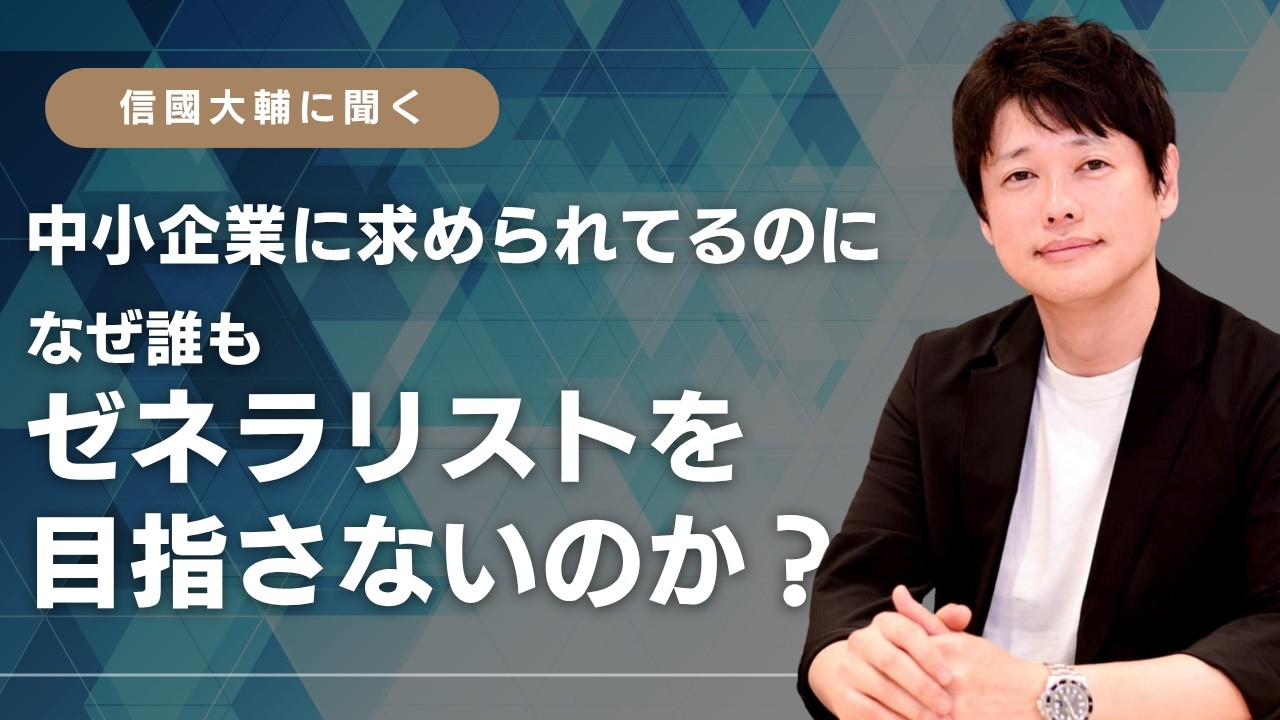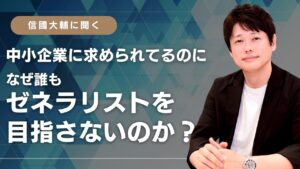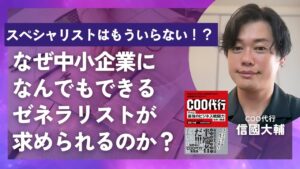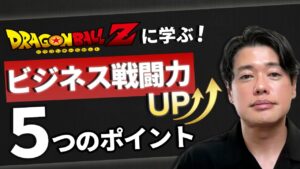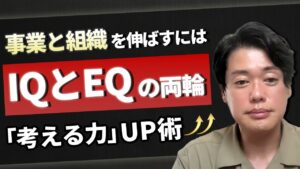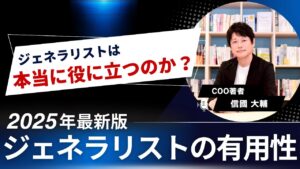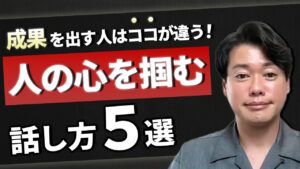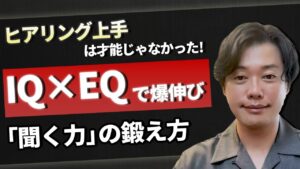現代のビジネス界では、「専門性を磨いてスペシャリストを目指せ」という声が主流です。
しかし、実は多くの企業、特に中小企業では、特定のスキルだけでなく、複数の領域に精通した「ゼネラリスト」が強く求められています。
なぜ、多くの人はこの貴重なキャリアパスを選ばないのでしょうか?
そして、ゼネラリストになることが、いかに自身の市場価値を高め、企業の成長に貢献するのかを解説します。
なぜゼネラリストは増えないのか?その裏に潜む4つの理由
動画では、ゼネラリストが不足している現状について、その背景にある心理的・社会的な理由を4つ挙げています。これらを理解することで、なぜゼネラリストが希少な存在であり、目指す価値があるのかが見えてきます。
1. 世の中がスペシャリストを推奨している
書店に並ぶビジネス書や、SNSで成功談として語られるのは、多くが「専門性を極めること」の重要性です。この情報過多な環境が、人々を「スペシャリストこそが成功の道」という思い込みに誘導しています。
2. 「すべてをこなすのは不可能」という心理
マーケティング、営業、経理、組織づくり…これら経営課題のすべてを一人でこなすことは、不可能だと多くの人が考えています。しかし、これは単なる思い込みであり、多岐にわたる知識をバランス良く身につけることで、企業のブランド戦略を包括的に推進する重要な役割を担うことができます。
3. 表面的な需要がスペシャリストに見える
企業が人材を募集する際、「採用のプロ」「マーケティングのプロ」といった専門家を求めることが多いため、ジェネラリストの需要が見えにくくなっています。しかし、中小企業においては、部門を横断して課題を解決できる多才な人材こそが、実は最も必要とされています。
4. 多面的な問題解決の価値が認識されていない
分業が当たり前の環境で働いていると、複数の問題を総合的に解決することの価値が理解されにくくなります。分かりやすい単一の問題解決(スペシャリスト)が評価されがちですが、ジェネラリストは、まるで健康問題における「食生活の見直し」のように、複数の要因から根本的な改善を図り、企業の持続的な成長という長期的なブランド価値を生み出すことができます。
希少な「ゼネラリスト」というキャリアを選択する価値
スペシャリストとして専門性を深めることは重要ですが、それに加えて隣接する領域の知識を広げることで、自身の市場価値を飛躍的に高めることができます。複数のスキルを統合し、全体を俯瞰して課題を解決できるゼネラリストこそが、現代のビジネス界で強く求められる人材なのです。