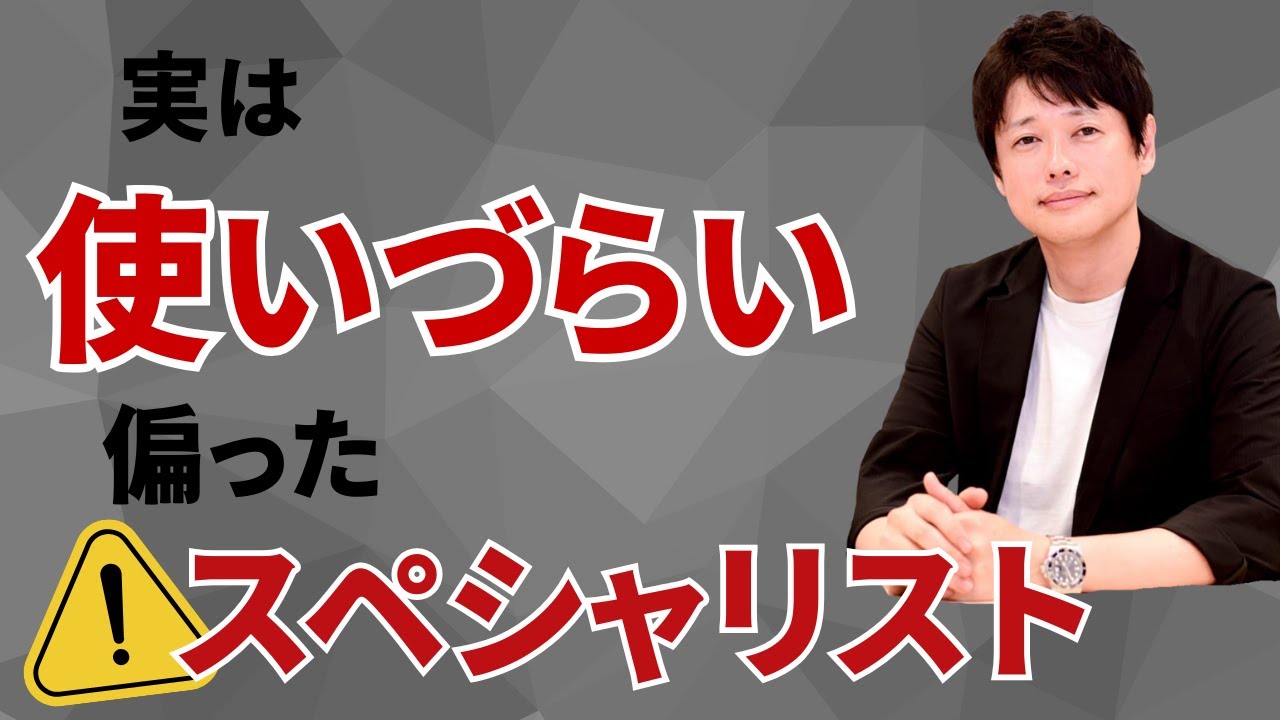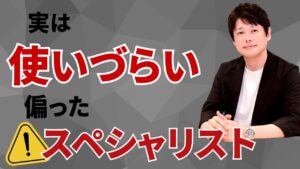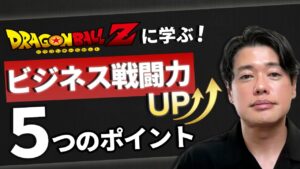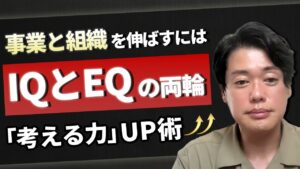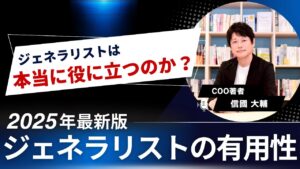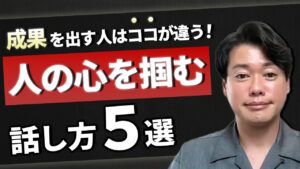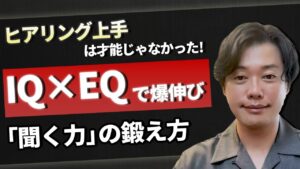「優秀な専門家を雇ったのに、なぜか事業が前に進まない」――中小企業の経営者が抱える、このような悩みの原因は、その専門家が「偏ったスペシャリスト」であることにあります。
この動画では、全体最適を見失い、部分的な成果しか出せない専門家たちの具体例を挙げながら、中小企業が本当に求める人材像を明らかにしています。
こんなスペシャリストは危険!部分最適に陥る専門家たち
動画では、以下の6つのタイプのスペシャリストが、中小企業の成長を阻害する可能性があると指摘しています。
1. 部分最適に特化しすぎたマーケター 派手で目を引くLP(ランディングページ)でリードは獲得できても、顧客の期待値が高まりすぎてしまい、その後の営業やサービス提供が困難になるケースがあります。これは、マーケティング単体では成功しているように見えても、事業全体ではマイナスになる「部分最適」の典型です。
2. デザイン重視のウェブデザイナー コンバージョンやマーケティングの知識がなく、「かっこいいだけのウェブサイト」を作成するデザイナーも同様です。ウェブサイトはマーケティング活動の一部であり、全体の戦略と連動していなければ、そのブランド価値を最大限に引き出すことはできません。
3. コミュニケーション能力が低いエンジニア 高い技術力があっても、現場の課題や要望を正確に把握できなければ、使い物にならないシステムを開発してしまうことがあります。特にITリテラシーが低いクライアントとの間で、この問題は顕著になります。
4. 管理が目的化したスタッフ 管理部門が「管理すること」を目的化してしまうと、営業やマーケティングの活動を妨げるようなルールを押し付けることがあります。本来、管理部門は事業全体のブランドを向上させるために、全体最適の視点を持つべきです。
5. 事業を理解していない税理士 企業のビジネスモデルを深く理解せず、過去の数字から杓子定規なアドバイスしかできない税理士も、中小企業にとっては使いづらい存在です。未来を予測するシミュレーションなど、経営に資する提案がなければ、その価値は限定的です。
6. 業績に無頓着な組織コンサルタント 企業の収益向上につながらない、理念やビジョン作りなどの間接的な取り組みに終始するコンサルタントも注意が必要です。耳障りの良い話で経営者をその気にさせても、最終的に業績が上がらなければ意味がありません。
中小企業が求めるのは「マルチスキル人材」
これらの課題を解決するためには、特定の専門性だけでなく、幅広い視点やスキルセットを身につけた「マルチスキル人材」、つまりゼネラリストが必要です。多角的な視点から事業を捉え、各部門を横断して課題を解決できるゼネラリストこそが、中小企業のブランド価値を高め、持続的な成長を牽引する存在なのです。